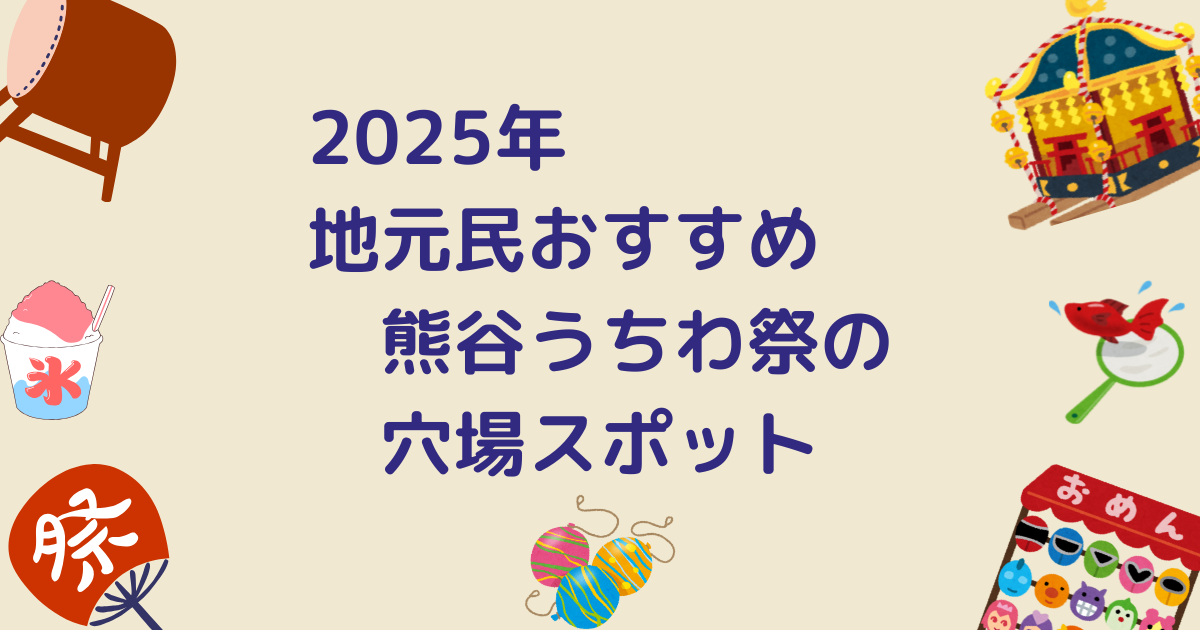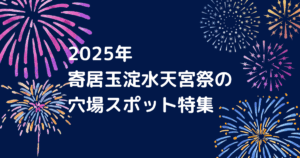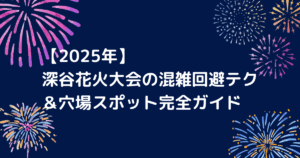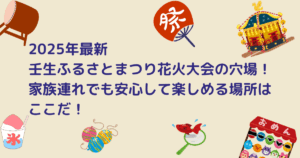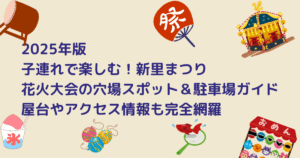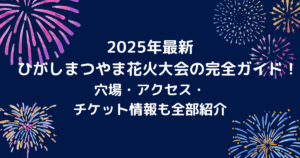夏になると、街を彩る祭りの賑わいが恋しくなりませんか?
そんなあなたにぴったりなのが、埼玉県熊谷市で開催される「熊谷うちわ祭」。
ただのお祭りと思ったら大間違い。
歴史と伝統、熱気と情熱がギュッと詰まったこの祭りは、毎年多くの人々を魅了し続けています。
とはいえ、有名なお祭りには付き物の「人混み問題」…「ちょっと落ち着いて楽しみたいんだけど」という声も多いのが現実。
そこで今回ご紹介するのは、地元民しか知らない“穴場スポット”の数々。
にぎやかさはそのままに、快適さをプラスした観覧場所やお役立ち情報を、徹底解説していきます。
歴史やアクセス方法、食べ歩きグルメから撮影ポイントまで、読み終えた頃には「よし、今年は熊谷行ってみようかな」と思っているはず!
それでは、熊谷うちわ祭の奥深い魅力へ、一緒に飛び込んでみましょう!
熊谷うちわ祭のおさらい
熊谷うちわ祭ってどんなお祭り?
熊谷うちわ祭は、毎年7月20日から22日にかけて行われる熊谷八坂神社の例大祭で、約270年の歴史を誇ります。
関東一の祇園とも言われるこのお祭りには、12基の山車と屋台が参加し、豪華絢爛な装飾と迫力あるお囃子が街を盛り上げます。
特に夜の提灯が灯された山車の行列は、幻想的な光景で観客の心をつかみます。
しかもこの祭り、ただ見るだけじゃありません。
うちわの無料配布があったり、地元の子供たちが太鼓を叩いたり、地域の人々が一体となって作り上げる“参加型”のお祭りなのです。
体験コーナーやフォトスポットも充実しており、一人で行っても、家族や友人と行っても満喫できます。
主な実施概要
・7月20日
渡御祭(とぎょさい)
神輿が御仮屋に向けて巡幸します。
時間:AM6:00~
場所:愛宕八坂神社〜市街地
初叩合い(はつたたきあい)
全町の山車・屋台が、熊谷駅を背に横一列に整列し、全町が揃って『初叩合い』をします。
時間:PM6:30~
場所:JR熊谷駅北口
・7月21日
巡行祭(じゅんこうさい)
国道十七号線が歩行者天国となり、山車・屋台は国道17号線を東に巡行。
市役所入り口交差点にて12基の山車・屋台が扇形に並ぶ。
時間:PM1:00〜PM3:30
場所:国道17号
・7月22日
行宮祭(あんぐうさい)
大総代が神輿を前に、祝詞奏上、玉串奉奠し、神の加護を祈願
時間:AM9:00〜AM11:00
場所:御仮屋(行宮)
曳っ合わせ(ひっかわせ)叩き合い
12基の山車・屋台がお祭り広場周辺に集まり、市役所入口交差点で扇形に整列し叩き合い
時間:PM8:00〜
場所:お祭り広場
年番送り(ねんばんおくり)
前年大総代による口上、その後「年番札」が送り渡されます。
時間:PM8:30〜
場所:お祭り広場
還御祭(かんぎょさい)
行宮から本宮まで神輿をおかえしする巡幸
時間:PM11:30~
場所:御仮屋〜本宮
うちわ祭りの魅力と見どころ
魅力は何と言っても「曳っ合わせ叩き合い(ひっかわせたたきあい)」。
これは最終日の夜、複数の山車が一か所に集まり、お囃子と太鼓で一斉に音を響かせる大迫力のシーン。
空気が震えるような太鼓の響き、提灯の光に浮かび上がる山車の影、それを見守る群衆の興奮――これぞうちわ祭の真骨頂です。
また、山車の上には地元の子供たちが乗り、太鼓を叩いたり手を振ったりとかわいらしい演出も。
日中は山車の展示や各町内の演技、夜には提灯と太鼓で彩られる幻想的な演出と、1日中飽きずに楽しめるのがうちわ祭の魅力です。
ここでチョット情報。うちわ祭りは勇壮な山車・屋台のお祭りなので花火大会はありません。花火を楽しみたい方は、以下ご覧ください。
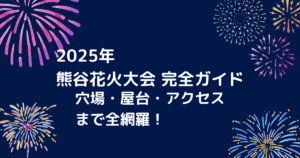
熊谷うちわ祭の歴史と伝統
うちわ祭の起源と変遷
熊谷うちわ祭の起源は、江戸時代中期の1750年頃にさかのぼります。
疫病退散、五穀豊穣、商売繁盛を祈願した祇園信仰がその始まりと言われてます。
それまでは地区ごと、各寺院ごとに行われた祭礼行事を統一の祭にしたいと願い出たのが始まりです。
当初は神輿祭り(みこしまつり)として定着していましたが、明治になり本町三・四(現在の第弐本町区)が山車を購入したことをきっかけに、各町でも山車・屋台を作成・購入していき、現在の形になりました。
また、明治時代のこのころ、地元の商人たちが来客にうちわを配るようになり、これが「うちわ祭」と呼ばれるきっかけです。
以降、祭りは年々盛大になり、現在では3日間にわたって約75万人の来場者を集める、埼玉県内でも最大級の夏祭りに成長しています。
今では「関東一の祇園」とも称されるようになりました。
地域ごとの特色や違い
熊谷うちわ祭には12の町会が参加し、それぞれが個性豊かな山車や装飾、演出で競い合います。
「銀座区」は熊谷次郎直実公の人形を乗せ、華やかさとエンタメ性を、「筑波区」は上段四方幕「白鳥の図」、下段三方幕「青龍の図」が山車を彩り、「仲町区」の山車人形は素戔嗚尊(すさのおのみこと)が飾られ、天女が描かれている見返り幕が張られています。
それぞれの山車には、町のシンボルや歴史的モチーフがあしらわれ、観る人の目を楽しませてくれます。
山車の運行ルートも日によって異なるため、全てを巡るには計画的な観覧が必要です。
各町内の工夫が光るこの“移動型芸術展”こそが、うちわ祭を一層魅力的なものにしている要素の一つです。
伝統的な祭りの意義
このお祭りは単なる夏のイベントではなく、地域に根ざした伝統文化の継承でもあります。
子どもたちはお囃子や太鼓の練習を通じて地域社会に参加し、大人たちは準備や運営を通じて交流を深めます。
特に、町ごとの山車づくりには多くの手間と技術がかかり、その過程こそが地域の絆を深める大切なプロセス。
さらに、祭りに関わることで自分の町に誇りを持ち、次の世代へとその文化が受け継がれていくのです。
つまり、熊谷うちわ祭とは「地域の魂」を感じられる場所であり、観光客にとっても“見るだけでなく感じる祭り”となっているのです。
熊谷うちわ祭の隠れた名所
周辺の歴史や文化について
熊谷市は、江戸時代には中山道の宿場町として栄えた場所。
うちわ祭の会場周辺には、今もその面影を残す町並みや、歴史的建造物が点在しています。
祭りの合間には、熊谷駅からほど近い「熊谷宿本陣跡」や、「熊谷堤」など、歴史好きにはたまらないスポット巡りもおすすめです。
おすすめの広場とその魅力
祭りをゆったりと楽しみたい方におすすめなのが「中央公園」。
比較的混雑が少なく、ベンチや木陰もあり、家族連れや高齢者にぴったりのスポットです。
また、「星川通り」の川沿いは提灯の明かりが水面に反射し、非常に幻想的。
人混みを避けながら、美しい光景を楽しみたい人に最適です。
知る人ぞ知る撮影スポットとして、カメラ愛好家の間でも密かに話題になっています。
特別なうちわと写真スポット
特別なうちわを探すコツ
熊谷うちわ祭期間中に、行宮へ参拝した方には『奉納うちわ』が配られます。
この『奉納うちわ』は、純国産!
国産うちわのシェア9割を誇る香川県丸亀市で製作された『丸亀うちわ』で、『仙賀紙』というハリが良く丈夫な和紙を、職人が一枚一枚手仕事で仕上げているもの。
数万本が配られるそうですが、早めの参拝するのが確実ですね。
また、さまざまな団体も限定デザインの特別なうちわを配布します。
中には商工会議所や地元企業のオリジナルデザイン、非売品バージョンも。
こちらも早めの時間に現地に到着することが秘訣です!
記念写真に最適な場所
うちわ祭りで写真映えを狙うなら、いくつかのおすすめスポットがあります。
まずは「八木橋百貨店」前の広場。
ここでは夜になると山車が停まり、背景に提灯が並ぶ幻想的な構図が撮れます。
また「熊谷駅南口のロータリー」では、駅舎と山車をセットで撮れるベストアングル。
さらに、少し高所から狙うなら「ティアラ21」のデッキが最適。
夜景と山車を一緒に収めることができる隠れスポットです。
カメラマンたちには定番の「星川通り」も、提灯が川面に反射するシーンが撮影でき、まるでアートのような写真に仕上がります。
今年の夏、浴衣で楽しむ花火大会はいかが?
せっかくの花火大会や夏祭り、思い出に残る特別な1日にしたいなら――
やっぱり「浴衣姿」で出かけたいですよね。でも「持っていない」「準備が面倒」「着付けが不安」…そんな理由であきらめていませんか?
そんなあなたにおすすめなのが、浴衣レンタルサービスです!
事前に好きな柄を選んで予約すれば、必要なアイテム一式(例:浴衣、帯、前板、腰ひもなど)がセット料金で届くから、手軽で安心。
しかも、往復送料は無料。
店舗によってはクリーニング不要で返却OKなところもあるから、アフターケアもラクちん!
気軽に借りて、浴衣姿で写真映えも◎
いつもの花火大会が、ぐっと華やかで特別な夏の思い出になりますよ。
→ 浴衣レンタルの詳細・予約はこちらから
周辺で楽しめる飲食スポット
地元名物を楽しむ飲食店
熊谷では、知る人ぞ知るB級グルメ「フライ」。
これは揚げ物ではなく、クレープのようなモチモチ食感の生地にネギや肉を包んで焼き上げたもの。
市内の「食堂いわ瀬」や「小山食堂」などで食べられます。
また、夏限定で提供される「雪くま」と呼ばれるふわふわかき氷も人気で、地元の天然水を使い、各店が独自のシロップをかけて提供しています。
他にも、熊谷産小麦を50パーセント以上使用し、熊谷で製麺された地産地消のブランドうどんの「熊谷うどん」もありますね。
熊谷うどんなら、エキナカの「熊たまや」や市役所近くの「元祖田舎っぺうどん」さんなどが人気です。
お土産には、文化庁にも100年続く食文化「100年フード」と認定された「五家宝」がおススメです。
屋台と人気メニュー紹介
お祭りといえば屋台もお楽しみのひとつ。
熊谷うちわ祭でも数百件の屋台が立ち並び、焼きそば・たこ焼き・チョコバナナなど定番のほか、「かき氷」や「焼きまんじゅう」(これは群馬かな?)といったご当地メニューも豊富です。
また、最近では外国人観光客向けに多言語対応メニューを掲示している屋台なども登場。
食べ歩き派には、たまりませんね。
お祭りの後に訪れたいカフェ
疲れた身体を休めるのに最適なのが、会場近くの隠れ家カフェたち。
熊谷駅から市役所までの間には地域の名店が散在してます。ここで、名物のかき氷「雪くま」で、好みの味探しを楽しむのもいいですね。
Wi-Fi完備していれば、SNSの投稿を一気に済ませるのにも便利。
また、駅近の「スターバックスコーヒー」や「ドトールコーヒー」など全国チェーンもあるので、慣れた味で安心したい方はこちらを利用しても良いでしょう。
夏の夕暮れ、うちわ片手にカフェで一息つく…それもまた、熊谷うちわ祭の素敵な楽しみ方のひとつです。
家族で楽しむ穴場スポット
子供連れにおすすめの場所
子どもと一緒に祭りを楽しみたいなら、「八木橋百貨店」の屋上の「キッズテラス屋上ガーデン」が特におすすめ。
オムツ替えスペースも完備されており、突然の「トイレ〜!」にも即対応可能。
屋上からは町が一望できるため、混雑に巻き込まれず、しかも涼しく快適に観覧できます。
「星川通り」沿いのベンチや木陰スペースは、小さなお子様を連れて一息つくのにぴったり。
シャボン玉や光るおもちゃを売る屋台も多く、子どもたちも飽きずに過ごせます。
星川沿いには「おやすみ処」も数か所設けられることもあり、親子で安心して参加できる配慮がされているのもポイントです。
おやすみ処と救護室の場所はこちら(熊谷うちわ祭りオフィシャルサイト)で確認できます。
安全に楽しむための注意点
お祭りの会場はとにかく人が多く、迷子になるリスクもゼロではありません。
事前に「はぐれた時の待ち合わせ場所」を決めておくと安心です。
また、子どもには目立つ色の服やリストバンド型の名前タグを付けておくと、万が一のときにも見つけやすくなります。
最近ではスマートタグをつける方法もありますね。
熱中症対策も忘れずに。
帽子、冷感タオル、水筒、そして時にはアイスやかき氷で小さなクールダウンを。
混雑のピークを避け、朝か夕方の時間帯に訪れるのも、安全に楽しむ工夫のひとつです。
「はぐれたらどうしよう」その不安に応えるGPS
人混みの中でのお出かけ。特に花火大会は、子どもがすぐ視界から消えてしまう心配も…。
そんな場面で活躍するのが、GPS見守りデバイス「まもサーチ3」です。
✔ スマホで子どもの位置をすぐに確認
✔ 移動履歴やエリア外通知もOK
✔ 家族で見守り情報を共有できるから連携もスムーズ
✔ 全国子ども会連合会推奨の信頼ある製品
さらに、「まもサーチ3」は日常の登下校や公園遊びにも使える月額サービス。
「イベント用の一時的な対策」ではなく、これからの見守り習慣のスタートにもぴったりです。
→ 今すぐチェックして安心を手に入れる
うちわ祭を満喫するためのポイント
荷物の持ち込み注意事項
お祭りといえば手ぶらが理想…とはいえ、夏の熊谷の暑さは想像以上。
持ち物にはちょっとした工夫が必要です。
おすすめの持ち物は、保冷ボトルに入れた飲み物、汗拭きシート、日焼け止め、携帯扇風機、そしてもちろん“うちわ”。
うちわは祭りの名物でありながら、実用性も抜群!
カバンは両手が空くリュックタイプが便利ですが、混雑時の接触を避けたいならボディバッグやサコッシュがおすすめ。
貴重品やスマホはジッパー付きのポケットに。大きな荷物やキャリーバッグは邪魔になるだけでなく、他の人の迷惑にもなるので避けた方が無難です。
また、撮影機材を持って行く場合は、三脚や一脚の使用が許可されているエリアを事前にチェックしましょう。
三脚を広げられない状況も多いため、ミニ三脚や手持ちでの工夫が必要です。
暑さ対策と服装の選び方
熊谷は「日本一暑い町」として知られるほどの猛暑地。7月のうちわ祭期間中は、昼間で35度を超えることも珍しくありません。
なにせ「暑いぞ熊谷」ですから。
そんな中でのお祭り参加には、暑さ対策が必須。
服装は通気性の良い綿素材のTシャツやリネンシャツがベスト。UVカット加工のある羽織物や、冷感インナーも重宝します。
足元は動きやすいスニーカーが基本。
サンダルは涼しいですが、人混みで足を踏まれるリスクがあるため要注意です。
帽子はつば広タイプを選び、首元には冷感タオルを巻くのが定番スタイル。
日傘は便利ですが、混雑エリアでは使用が制限されることもあるため、できれば帽子で日除けを確保するのが無難です。
限られた時間での楽しみ方
「平日で仕事が終わったあとしか行けない…」という方も多いはず。
でも大丈夫!熊谷うちわ祭は夜まで楽しめる仕掛けが満載です。
特に20時以降には山車が一堂に集まり、「曳っ合わせ叩き合い」がクライマックスを迎えます。
これを見逃さなければ、短時間でもお祭りの醍醐味を味わえます。
また、公式ガイドマップを事前にチェックして、目的のイベントやエリアを絞り込んでおくことで、滞在時間を効率的に使うことができます。
写真を撮るなら提灯が灯る時間帯がベストなので、タイミングを見計らって移動しましょう。
そうそう、うちわ祭りは日によって巡幸するルートが違うんです。また、12基の山車・屋台の位置もそれぞれ。
そのため、お祭り期間中は、山車・屋台がどこにいるかリアルタイムでわかるマップが公開されます。
それが、このマップ。このマップがあれば、お目当ての山車・屋台の現在地が一目瞭然です。
加えて、移動時間や帰宅時間も考慮し、あらかじめ電車の時刻表や混雑予想を確認しておくと、ストレスなく楽しめます。
駅のロッカーは早めに埋まるので、必要であれば駅周辺のコインロッカー情報も調べておくと便利です。
交通規制の詳細と影響
祭り期間中は、駅から会場までの主要道路を中心に大規模な交通規制が行われます。
主な交通規制
・7月20日
>>星川通り(一部)18時から18時30分まで
>>駅通り(熊谷駅北口広場~国道17号筑波交差点)18時30分から20時まで
・7月21日
>>市街地 13時から21時まで
>>国道17号 13時から21時まで
・7月22日
>>星川通り(一部) 9時から11時まで
>>市街地 13時から22時まで
>>国道17号 18時から21時まで
午後から夜にかけては車両通行止めになるエリアが多く、地元民でも「今日はチャリで移動だな…」と自転車に乗り換えるほど。
また、バス路線も一部が変更されたり、運行休止になることもあるため、事前に熊谷市の公式HPや観光協会のサイトで交通規制マップを確認しておくと安心です。
特に熊谷駅北口から祭り会場へ向かう道路は、人の波でなかなか進めないほどの混雑となるので、時間に余裕を持った行動を心がけましょう。
交通アクセスと駐車場情報
公共交通機関の利用方法
熊谷駅はJR高崎線、秩父鉄道が通っており、また新幹線の停車駅でもあるため、都心からのアクセスは抜群。
東京駅から熊谷までは約70分、新幹線ならさらに短縮され、熊谷までわずか40分程度で到着できます。
東京方面からだけでなく、高崎や前橋といった群馬エリアからのアクセスも良好。
祭り期間中は駅構内にも案内看板が増え、駅での誘導も強化されるため、初めての来訪者でも安心です。
また、うちわ祭の期間中は特別ダイヤが組まれたり、秩父鉄道で臨時列車が運行されることも。
夜間のイベントに参加しても帰れるよう、最終列車の時間を事前に確認しておくのがベストです。
さらに、熊谷駅から会場までは徒歩5分程度と近く、車よりも公共交通機関の方が圧倒的に便利と言えるでしょう。
無料駐車場
当日、臨時の無料駐車場が設けられます。
ただ、例年大変混雑するので、早めの確保が必要です。
- 市役所駐車場(宮町二丁目47番地1) 17時15分から23時
- 熊谷地方庁舎(末広三丁目9番地1) 17時15分から23時
- 八木橋第1駐車場(本石1丁目294) 19時から23時
- 八木橋第4駐車場(仲町45番地2) 19時から23時
- イオン駐車場(本石2丁目135) 19時から23時
パーク&ライド
お祭り会場周辺の渋滞対策として、「熊谷スポーツ文化公園西多目的広場」と「熊谷駅北口」を約30分間隔で無料バスが運行されます。(駐車場も無料です。)
バス停はスポーツ文化公園西多目的広場と熊谷駅北口だけで、途中乗車・下車はできませんが、事前予約や申し込みは不要なので、利用するのも一案です。
詳しくは、(一社)熊谷市観光協会ホームページをご覧ください。
周辺駐車場の比較と予約情報
車で来場する場合、中心部の駐車場は非常に混雑します。
特に午後から夜にかけては満車が続出するため、事前の計画が必須です。
私のとっておきの穴場情報は、熊谷駅の南口側にある民間駐車場。
南口には多くの民間駐車場があり、通常は一日500円程度で利用できます。
それぞれ、大きい駐車場ではありませんが、駅北口の混雑とはくらべものにはなりません。
お祭り当日も焦らず安心!akippaで駐車場をキープ
ただ、南口の駐車場でも、やはり時間が遅くなれば、満車となります。
近年では、akippa(アキッパ)など、スマホで簡単に予約できる駐車場サービスの活用が増えています。
現地で駐車場を探すよりも、事前に駐車スペースを確保したい方には便利なサービスです。
混雑を避けるための裏技
何と言っても混雑のピークは夕方5時から9時ぐらいに集中します。
その時間帯を避けることで、比較的スムーズな移動が可能に。
おすすめの裏技としては、早朝に到着して午前中の散策を楽しむプラン。
または、あえて遅めの時間に訪れ、夜の雰囲気だけを楽しむ「遅刻参加」スタイルもありです。
また、熊谷駅周辺ではなく、ひと駅手前の「行田駅」や「籠原駅」に車を停めて電車で熊谷駅に向かうという“パーク&ライド”方式はかなり有効。
これなら渋滞を避けられ、駅周辺の混雑にも巻き込まれにくくなります。
まとめ
熊谷うちわ祭は、ただの夏祭りではありません。地域の熱意と伝統が詰まった、まさに“生きた文化遺産”。
特に3日間の開催のうち、最終日の夜に繰り広げられる「曳っ合わせ叩き合い」は、魂が震えるほどの迫力です。
全身で感じる太鼓の振動、幻想的な提灯の明かり…それらは他のどんなイベントでも味わえない“非日常”の体験です。
この記事では、混雑が心配な方でも快適に楽しめる穴場スポットや、アクセス・駐車のコツをたっぷりとご紹介しました。
皆さんが楽しく過ごせる手助けになれば幸いです。
特に小さなお子様連れや、高齢の方と一緒に訪れる場合には、混雑回避の工夫や休憩スポットの情報が重要になってきます。
ぜひ参考にして、事前準備をしっかり整えて、最高の夏の思い出を作ってください。
うちわ片手に、今年の夏は熊谷で思いっきり熱くなってみませんか?祭りの風に吹かれて、きっと忘れられない夏の一日になることでしょう!